頭が悪いわけじゃない
読書していても、文字を追ってるだけで内容が全然頭に入らないことってありますよね。
え、読めないって俺の頭が悪いってこと!?

って、難しい本を読み始めた中学の頃、愕然としたものです。
でもこれって自分の能力が低いわけじゃないんですよ。
今の現状の自分に合っていないだけです。
自分は自分だと思っていますし、未来になってそう変わるもんだと思わないものです。
つまり読書数で「自分」なんて簡単に変わるんです。
自分のわかる本だけを読んでいくといつの間にか、分からなかったはずの本が読めるようになるものです。
だからどうしても分からなければ別の本を読みましょう。
漱石だって
二三ページ読むと眠くなる。涎を本の上へ垂らす。これが彼の毎夜繰り返す日課である。
と『吾輩は猫である』で漱石自身がモデルのクシャミ先生の様子を書いてあります。
漱石は現代文を作ったといえるくらいの文学者です。
日本語だけでなく、英語は帝国大学の教授ですし、漢文も漢詩が書けて、しかもその出来は本場の中国人レベル。
漱石だってそうなんですから、我々もこういうことがあっていいんです。
読む気が失せたら別の本を読むか、別のことをしましょう。
「気にしない」という事が重要です。
漱石の凄さ
ちなみに「漢詩が書ける」っていうのはすごいことです。
日本人が古代中国人の言葉である漢詩を書けるって、文法が分かるとかそういうレベルではなく、心情まで書き表せるってこと。
歴代、日本人でも漢詩を作成した人はたくさんいますけど、漱石と河上肇くらいしかちゃんとした漢詩作家はいないと言われるくらい。
そんな漱石が「二三ページ読むと眠くなる。」日課だと言ってるんです。
つまり「読めない」ってことは普通ですよ。普通。
興味のある分野を読もう
大作家でもそうなんですから、全員、読書に集中できなくて当然。
読書は、興味のある分野でなければ頭に入りません。
興味を持てる分野は、それに関しての知識がないと興味を持てません。
知識は構造的(お互いが関係しあっている)なものなので、少しでもその分野を知っていれば興味が持てるもんなんですね。
【関連記事】
ですから何か本を読むときに、
- 「流行っているから」
- 「有名だから」
という理由だけで買って読んでみると、1ページも頭に入らないなんてことが起きるんです。
その場合は、相性があっていないので、変に粘らずに別の本を読みましょう。
あとは不思議ですが、
「わからない、わからない」
と思いながら字を追っていた本を日を改めてもう一度読んでみると、一回目よりも理解ができていることがあります。
全く理解ができていないと思いながらも、慣れない言葉、単語に少しずつ慣れて理解ができるようになるんです。
でもそれは複数回読まないと体感できないことです。
さらにアウトプットするとなるとそのまま、理解ができないままです。
一回気になって読み始めた本は、無理に読まなくてもいいですが、ふとした時に、まだ記憶があるうちに読み返してみると理解ができている不思議な体験が味わえます。
自分に合った本を見つけるなら、立ち読みをドンドンして自分にとってピンとくるものから読んだほうがいいです。
小説の場合はそういうことがよくあります。
「くだらない」って思っちゃうんですね。
自分に身近な話じゃなかったり、簡単な構造に思える、誰でも理解ができそうなものはなかなか興味が持てません。
私は古典や純文学をよく読みますが、流行の大衆文学はほとんど読みません。
そんな歯ごたえのある文学を読む場合はすぐに理解ができないんですよね。
そういう時、私はまずは漫画をお勧めします。
なぜかといえば大よその話の流れを知っていれば理解が早まるからですね。
古典や純文学はストーリーだけがおもしろいのではありません。
むしろ、そこではなくて細かな描写や言葉の使い方に面白さがあるんです。漫画でストーリーを先に知ってしまえばそこに気を配れるようになります。
が、やはり漫画版だからと言って興味の持てないものは全然読む気になりません。
小説嫌いの人の理由の中で「作り物だから」「くだらないから」というのはハナからその分野、書かれている人間関係に興味が持てないからです。
小説と言っても色々あるのでたくさん読んでいれば興味が持てるものが絶対になるはずなんです。
でもそんなにたくさんの分野を一度に知ることはなかなか難しいもんです。
そういう場合は「まんがで読破シリーズ」をお勧めしています。
【関連記事】
なぜなら古典的名作を一冊に凝縮していますから、大体の内容がそれで分かるんですね。
小説って本当にくだらない代物かっていうと、そんなことないんですよ。
でもすぐに効果が出るものではないんですね。
【関連記事】
人の上に立つなら小説がいい
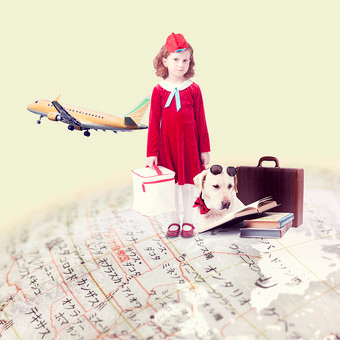
人の下で働いている、部下の状態であれば小説はあまり関係ないかもしれません。
小説は頭に入らないけど、実用書ならスラスラいけるという人が多いんじゃないでしょうか。
それは大概、その分野に関する知識を持っているからでしょう。
本は知識で読むものなので、その分野に詳しければスラスラ行けるはずです。
しかし実用書とは、あくまで仕事をする上での具体的な知識であって、それ以上の抽象的な思考に至るには力不足です。
しかし人の下で働いているだけならそれで問題ないでしょう。
その場合は、より良い手足である必要があるので色んな知識がいるでしょうから新書をたくさん読んでいればいいんです。
【関連記事】
でも人の上に立ったり、独立して生きる場合には小説は必要だと思います。
なぜかといえば小説は「解釈する力」が付くからです。
人の下で働いてるなら、上の人の考えを注入されて生きてればいいです。
しかし上に立つとなると生きていくうえでの問題を自分で解決しなければなりません。
【関連記事】
解決するには正解があればいいですが、正解なんか学校のテストじゃないんですから普通はあるはずありません。
役所などの官僚が自分で解決できないのはそういう理由があります。
自分で解決しちゃいけないようになってるんですね。
法律というのは人が作ったものを順守するものです。法律になければ前例です。
前例を作ることは法律を作ることに準じます。ほぼ法律と言っていいでしょう。
官僚は公僕、つまり公の下僕なので勝手な法律解釈はできないというシガラミもあるんですね。
そうでもない限り小説は読んだほうがいいです。一朝一夕に能力が付くわけではないので。
解釈入門の小説
分かりやすいのであれば、ルナールの『にんじん』なんか面白いかもしれません。
短くてすわかりやすいです。
これは三人兄弟の末っ子「にんじん」(赤毛でソバカスがついているから)が主に母親から虐待を受けるという話です。
何がいいかというと、普通に読んだら児童虐待で、それが解決されるわけでない話なので
- 「かわいそうだ」
- 「理不尽だ」
- 「救われない話だ」
という感想しか持ちません。
児童文学にもなっているので子供は普通
「かわいそうだ、それにくらべてぼくは・・・」
云々、くらいでおわります。
かと言って、大の大人が読んでもそれくらいで普通は終わります。
大人だろうが解釈できる力がついていなければ仕方ないからですね。
これってどういう解釈ができるって、よくよく読んでいたら後半になればなるほど反発しているんですね。はじめは精神的にではなく肉体的にです。
頭の癖っ毛を直すためにポマードをつけられるんです。
それでも髪の毛は立ってしまいます。
これは家族がどうやっても主人公である「にんじん」を制御することができないことを象徴するシーンになっているんです。
しかし一回読んだだけでは、ただただ無理やりポマードをつけられて
「虐待されている、かわいそうだ」
の一点張りで読み進めてしまいます。
こういう、いろんな解釈をするには他の人の読み方を知ったほうが効率がいいので文庫の後ろに付録されてる「解説」を先に読んだら読みが深まります。
光文社版の訳者の「あとがきのあとがき」がネットで公開されているのでそれを読んでみたら面白いと思います。
【関連記事】







